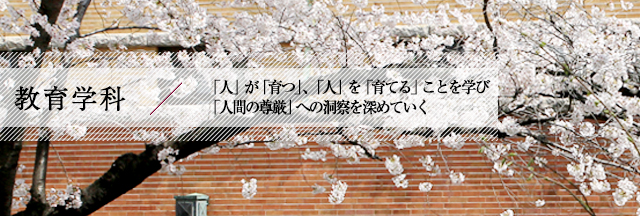上智大学の教育学専攻は、研究者養成、高度職業人の養成の両面で優れた成果をあげています。
そのごく一部ですが、修了された方々の声をまとめております。
Voices from graduates in the English-track couse
博士前期課程を修了した院生の進路と声
相澤真一教授
-

-
小池 明子(こいけ あきこ)さん
経歴 2023年教育学専攻博士前期課程(修士)修了
修士論文のタイトル:「地域の教育構造と私立中学校選択の相互作用―『脱出(Exit)』・『意見表明(Voice)』・『忠誠(Loyalty)』モデルによる検討―」
卒業後の進路:日本私立学校振興・共済事業団メッセージ自分が経験した私立中学校進学という事象には、社会的な不平等が深く関わっているのではないだろうか。そんなぼんやりとした、しかし無視しがたい感覚が、上智大学大学院で教育学を専攻するきっかけになりました。大学院に進学してよかったと思うことの1つは、「何かおかしい」、「困っている」、「何とかしたい」等々の感覚、つまり問題に対する感受性を鈍らせることなく、そのような自分の問題関心を、ほかの人にも了解可能な形で説明するトレーニングの機会を得られたことです。ゼミでの議論や修士論文の執筆を通じて、ささやかにでも、自分の問題意識を言葉で共有する手応えを掴めたことは、貴重な経験でした。今後は問題提起の先のこと、他者を巻き込みながらの問題解決という段階にも挑戦したいと考えています。大学院での学びが、きっと支えになるはずです。
上野正道教授
-

-
張 佳琳(ちょう かりん)さん
経歴 2022年教育学博士前期課程(修士)修了
修士論文のタイトル:「多文化共生社会における学校カリキュラムと批判的リテラシーの形成―国語科教育を中心として―」
卒業後の進路:東京都公立学校 高等学校教諭(国語)メッセージ教育学科の必修科目の中で、学校教育における外国にルーツを持つ子どもたちのおかれた状況について知り、その後も自分の中で「気になる」こととして残っていたこの課題を卒業論文のテーマにしました。私には、卒業後は外国にルーツを持つ子どもたちの力になりたいという漠然とした思いがありましたが、次第に、高い専門性を持った教員になりたいと考えるようになり、上智大学大学院の教育学専攻に進学しました。在学中は、多様な背景を持った学生たちとともに、学校教育学に関する知見を深めることができました。また、社会科免許状を基礎として、国語の免許状を取得し、中学校・高等学校への訪問や支援員としての経験から考えることを通して、多角的な視点から考えることの重要性について学びました。修士論文では、『現代文B』の教科書の題材における多文化性に着目し、個々の題材を多文化共生の観点から考察するという研究を行いました。今後は教員という立場を生かし、学校教育の現場から実践や検討を重ねることができるのではないかと思っています。多文化状況が加速している今日の学校教育において、国語科教育における多文化教育について、研究と実践のつながりを見出していけるよう、これからも学び続ける人でいたいと考えています。
小松太郎教授
-

-
郡山 文(こおりやま ふみ)さん
経歴 2023年教育学博士前期課程(修士)修了、大学院在籍中にJICA横浜に勤務、2児の母
修士論文のタイトル:「マダガスカルの若者ボランティアの特徴、動機とキャリア形成 -ローカル NGO Teach For Madagascar を事例として-」
卒業後の進路:ブラジルのローカルNGOにてボランティア活動メッセージ国際協力の仕事に携わる中で、国際教育開発を理論面から見つめ直し、住民主体の教育開発について知見を深めたいと思い、第1子の妊娠中に教育学専攻への進学を決意しました。そして1年目を修了したタイミングで、仕事の都合で1年間休学し、復学した修士2年目の時に第2子を出産しました。多様な専門性を兼ね備える本専攻の先生方のもとで、幅広い年齢層と国籍を有する院生同士との関わりから、多くの学びが得られました。育児と仕事に加えて学業を両立させることは、もちろん苦労もありましたが、“学ぶ”ということが心から楽しいと思えたのは、指導教官並びに先生方や事務の方、院生からの柔軟で温かなサポートを常に得られたことと家族の支えのおかげです。今後は、ゼミでの議論や研究を通じて得られた気づきと学びを、国際協力の現場へ還元し、実務者として多角的な視点で取り組んでいきたいと考えています。
-

-
長内 淑江(おさない よしえ)さん
経歴 2021年教育学博士前期課程(修士)修了
修士論文のタイトル:「開発途上国のノンフォーマル教育の意義―ストリートチルドレンを対象としたネパール現地 NGOのノンフォーマル教育プログラム担当スタッフの意識と役割に着目して―」
卒業後の進路:公益社団法人シャンティ国際ボランティア会事業サポート課メッセージ教育の機会を十分に得られない子どもたちへ教育の機会を提供するためのサポートがしたいと思い、そのための専門性を身に付けるため、上智大学大学院の教育学専攻に進学しました。国際教育開発学に関する知見を学ぶことができただけではなく、教育や社会を多面的な視点から考える力や課題を見つけて調査し、表現する力を身に付けることができたと思います。また、在学中にはアジアの教育支援活動を行っているNGO団体、シャンティ国際ボランティア会でインターンをさせていただき、修了後の進路や大学院での学びをどう活かしていきたいかをより具体的にイメージすることができました。大学院で身に付けた専門性や大学院生だからこそできた経験を今後に活かし、子どもたちに必要な教育の機会を提供するための支援ができるよう、努めていきたいと思います。
-

-
須藤 玲(すどう れい)さん
経歴 2020年教育学博士前期課程(修士)修了
修士論文のタイトル:「東ティモール教授言語政策の政策形成過程におけるポリティクス―「母語を基礎とする多言語教育(MTB-MLE)」の政策形成過程を事例に―」
卒業後の進路:東京大学大学院教育学研究科博士課程に進学。令和2年度日本学術振興会特別研究員(DC1)。メッセージ東ティモールの教育問題に実務者として携わりたいという目標の下、まずは教育学を軸とした専門性を身に付ける必要があると考え、上智大学大学院の教育学専攻に進学しました。指導教官による指導の下、国際教育開発学に関する知見を深めることができただけでなく、本専攻の特徴の一つである、教員の研究分野の多様性を活用し、広く深く教育学を学ぶことができました。修士論文では、東ティモールの教授言語問題に焦点を当て、現地調査で収集したデータを基に、当国の教育政策を取り巻くポリティクスについて明らかにすべく分析を行いました。修士課程での学びの醍醐味は、より高度な講義やゼミの内容にあるだけでなく、こうした講義やゼミにおける院生同士での議論(学びあい)にこそ価値があると思います。本専攻は少人数であり、どの授業でも活発に議論がなされ、その議論から自身も多くの学びを得ることができました。修士課程での学びがあったからこそ、国際協力に携わるうえで、高度な専門性がより求められていることを痛感しました。今後も教育学において卓越した専門性を身に付け、将来的には東ティモールの教育問題にアプローチできるような人になりたいと考えています。
-
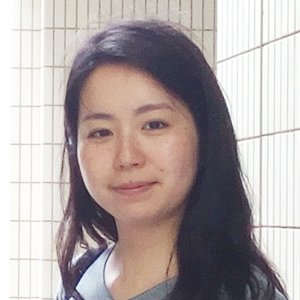
-
酒井 春佳(さかい はるか)さん
経歴 2019年教育学博士前期課程(修士)修了、大学院在籍中に在レバノン日本大使館に勤務
修士論文のタイトル:「レバノン共和国に居住するシリア難民の自尊感情検討―公立校編入前教育で学ぶ子どもに着目して―」
卒業後の進路:国際協力機構(JICA)青年海外協力隊事務局メッセージ紛争影響国の教育復興に実務者として携わりたいという夢を叶えるべく、その前に専門性を身につけたいと思い、上智大学大学院の教育学専攻を選びました。同専攻のゼミは10人以下の少人数で行われることが多く、自ら考え発信することが日々求められます。また、アジアや欧米からの留学生も多数参加するため、英語でのディスカッションを通じて語学を鍛える良い機会となりました。自身の研究では、レバノンにいるシリア難民の子どもの自尊感情検討を、現場調査を通じ混合手法を用いて実施しました。大学院での学び=専門性のメガネを得ることだと考えています。社会人になっても、俯瞰的に専門性のメガネで物事を分析することが、今後の国際協力を考え進めていく上で必須だと考えています。
Profiles of previously supervised students
Prof. Taro Komatsu
-

-
Andrea Mrazović
I have been working as a biology and science teacher in Croatia for a couple of years when I came to Japan as part of my professional development. There I developed an interest in education beyond teaching and I came across Professor Komatsu's work. I am particularly interested in the relationship between education and social issues such as gender equality, women's rights, and social justice.
During my time at Sophia University, I shaped my views on education and fostered a multidisciplinary approach. In addition to the courses at the Department of Education, I often took courses from other departments as well as from United Nations University in Tokyo which gave me a valuable insight into the work of the cardinal international organization and its perspectives on education. Moreover, I presented my research at the International Educational Development Forum in Tokyo and earned a Joint Diploma from Sophia University and United Nations University together with my Master's degree. Studying at Sophia has been a valuable experience also because of the multicultural environment and discussion-oriented approach in small groups where everybody was given the opportunity to speak out.
Unfortunately, due to the global pandemic during my 2nd year, the opportunities to become involved in practical work or internships were scarce, but luckily the classes at Sophia went on online uninterruptedly. At the moment, I am in Europe where I was offered a position at an international school.
-

-
Flora Mon
My name is Flora from Myanmar (Burma). As I was stepping into the field of education, I wanted to learn about how our country can be developed through education. Being affected by internal conflict (both violent and non-violent), Myanmar needs education and educators that could bring peace. And I wanted to become one of such educators. Hence, I decided to pursue Master’s in Education at Sophia University, with the focus on educational development. In Sophia University’s education program, courses related to International Education and Educational development are offered in English. Wide range of elective courses conducted in English are also offered from other faculties. We had good opportunity to learn from professors who are not only academic scholars but also practitioners. This enhances our learning experiences beyond theories. Occasionally, we were also provided with opportunities to learn from visiting scholars, professors, and practitioners from abroad. Moreover, I was fortunate to study together with both Japanese and international students who come from different countries of Asia, Africa, America and Europe. That gave us opportunity to learn some educational and cultural practices from each other’s country. Having studied in Education program at Sophia University prepared me to share about how school education could impact peace and conflict, and consequently development with student teachers at a teacher training school in Myanmar where I will be teaching.
-

-
Fred Emmanuel Sato
My name is Fred Emmanuel Sato and I come from Malawi. When I decided to advance my academic knowledge on how education impacts development and came across Sophia University Department of Education’s curriculum, it fitted well into my ambition. Graduate studies at the department extensively cover content on education and development including education in emergencies, global citizenship education, inclusive education, comparative education and educational research. Sophia University is a truly international institution with a lot of English-speaking students, staff and, therefore, English support for international students. During seminars, professors gave us time and freedom to share content-related insights from our respective countries. This gave me rich knowledge on education in different contexts, developed and developing alike.
The department also offered me information and other opportunities through my supervisor Professor Taro Komatsu. I attended a conference organized by the Japan Society on African Education Research (JSAER) at the International Christian University in Tokyo, travelled on an research support trip to Cape Town, South Africa and had an internship opportunity with UNESCO in Addis Ababa, Ethiopia. Through a special academic arrangement that Sophia University has with the United Nations University (UNU) in Tokyo, I studied for a joint intensive Diploma in Sustainability Science alongside my MA. I learnt a lot about the UN System and sustainable development.
Sophia University’s Department of Education gave me the knowledge and experience I needed, and even more. I would not hesitate to urge anyone looking to study education and development to join the Department.
-

-
Yingyi Guo
I had been volunteering and teaching in Thailand for four years, during which I became particularly interested in the use of educational aid as a means of cooperation between Asian countries. Following this, I discovered Prof. Komatsu's research direction and I believe it to be an excellent fit for me because of its emphasis on understanding how education affects social cohesion and peace, as well as international aid to education.
Through my studies in the fields of education and international development, I have gained a theoretical understanding of educational issues and their relationship with poverty, conflicts and diversity in developing countries. By exploring how these issues can be addressed from both domestic and international perspectives, I have become more aware of the importance of enhancing the quality of education through teacher capacity-building and by making improvements to curriculum design and assessment systems. As part of my master’s research, I conducted an independent study on Japan’s educational assistance to Thai universities.
During the summer break of 2019 I joined UNESCO Bangkok as the first intern from Sophia University. Thanks to this internship, I was able to acquire an in-depth understanding and the practical experience necessary for the coordination and organization of educational improvement activities. During the preparation of UNESCO’s regional seminars and meetings, I further developed my communication and writing skills as I was assigned to liaise with participants, engage in advocacy, and produce outreach materials. All the new skills, knowledge and information I gained from my internship with UNESCO will be very helpful in pursuing my study as well as in developing my future career. Currently, I am in the final stage of the hiring process with an EdTech company in Tokyo, but the situation has been significantly delayed because of COVID-19.